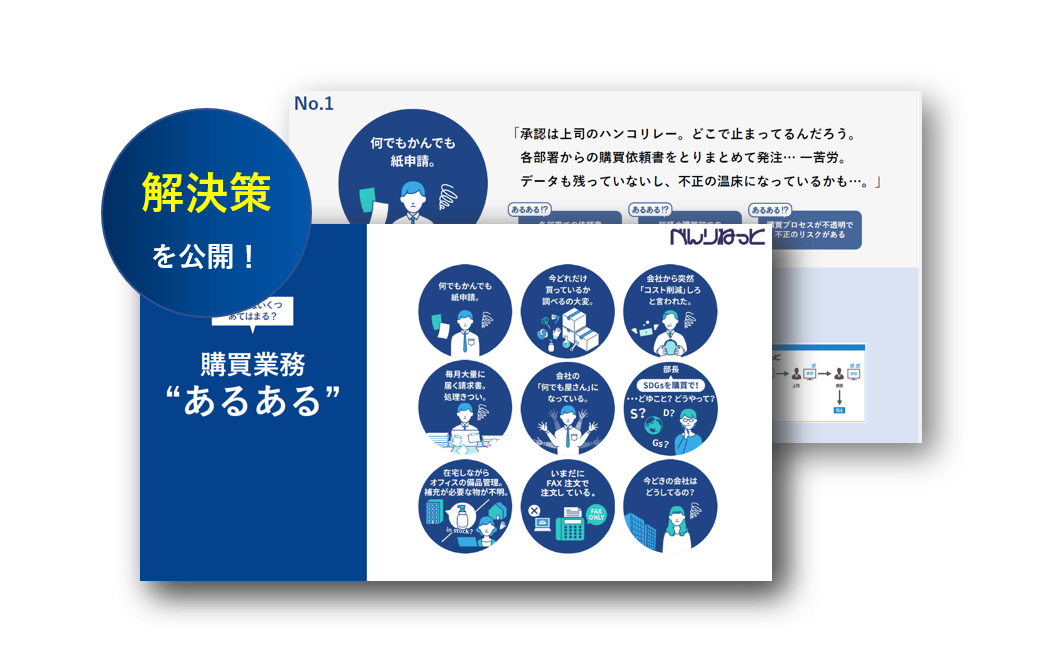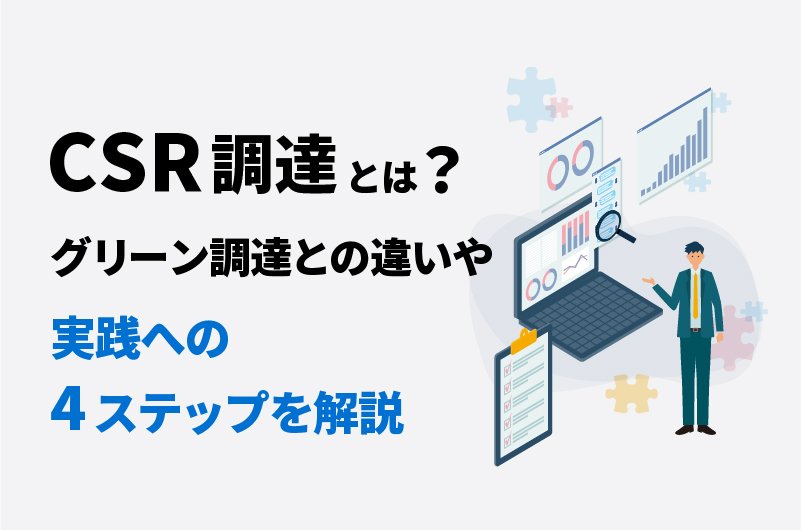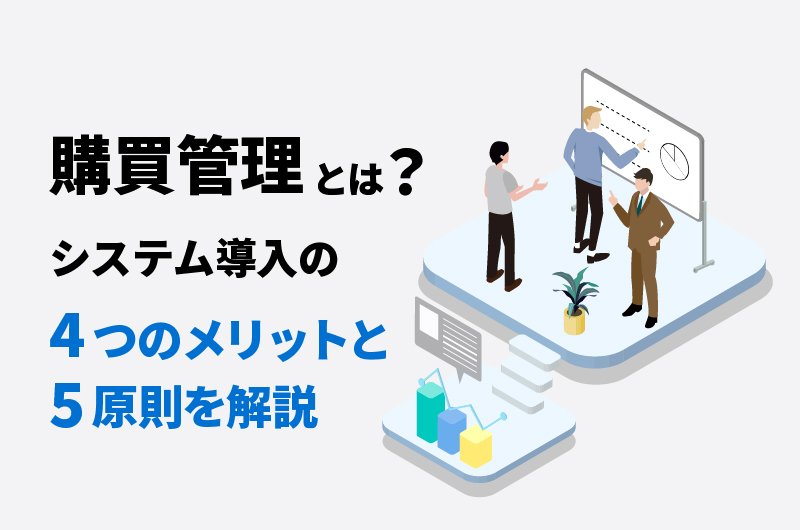副資材とは?管理が難しい4つの理由と効率化に役立つツールを紹介
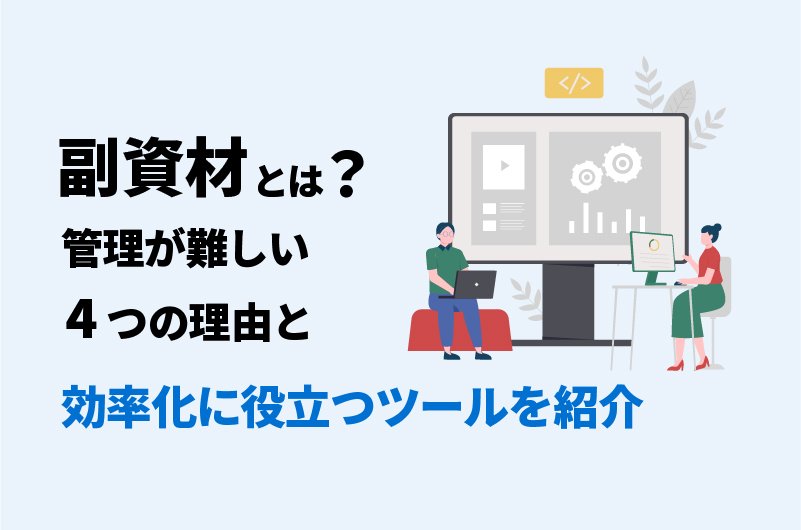
公開日:
副資材(MRO)の購買管理は多くの企業で軽視されがちですが、生産性や収益性を左右する重要な課題です。適切な管理体制を構築することで、コスト削減や業務効率化、内部統制の強化に貢献します。
本記事では、副資材の管理が難しい4つの理由と管理不足によって起こり得る4つのリスクを解説しています。副資材の購買管理に役立つツールについても紹介しているので、購買管理に課題を感じている方はぜひ参考にしてみてください。
目次
副資材(MRO)とは?

副資材とは、製品の製造に直接関与しないものの、生産プロセスや設備維持に必要な間接材を指します。
「Maintenance(メンテナンス)」「Repair(修理)」「Operation(運用)」の頭文字を取ってMROと呼ばれることもあります。
副資材に含まれる具体的な資材について、以下にまとめました。
| 資材 | 具体例 |
| 消耗品 | マスク・トイレットペーパー |
| 事務用品 | 文房具・用紙 |
| 工具 | ドリル・測定器具 |
| 保全用品 | パイプ・鉄板・釘 |
| 燃料・化学薬品 | 溶接用ガス・清掃剤 |
主資材(直接剤)が製品の原材料・部品(例:自動車の鋼板)であることに対し、副資材は生産現場やオフィスで使用される備品や消耗品を指します。
副資材の購買管理に課題を感じている方は、以下の記事もご参考ください。管理におすすめのツールについても詳しく解説しています。
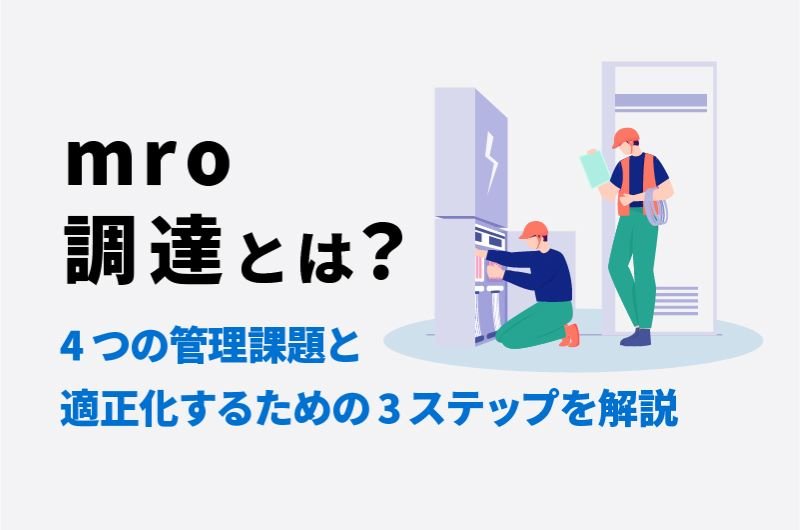
✓ 関連記事もチェック
MRO調達とは?4つの管理課題と適正化するための3ステップを解説 >>
MRO調達が抱える課題や適正化のための取り組み、購買管理システムの導入メリットを解説。
副資材の管理が難しい4つの理由

副資材の管理が難しい理由として、以下の4つがあげられます。
- 品目の多様性により管理が煩雑になりやすい
- 発注する部署・人が分散している
- コスト管理が難しい
- 主資材に比べて優先度が低い
副資材の管理上の特徴を明確にし、適切な管理方法を検討しましょう。
副資材の購買管理を適正化したいとお考えの方は、以下の記事をチェックしてみてください。

✓ 関連記事もチェック
間接材とは?直接材との違いや購買管理の適正化の4ステップを解説 >>
間接材の特徴や適正化のための4ステップを解説。
これから購買管理に着手する方には、以下の資料がおすすめです。課題の抽出から改善までの手順を具体的に解説しているので、ご自身や社内での情報共有にお役立てください
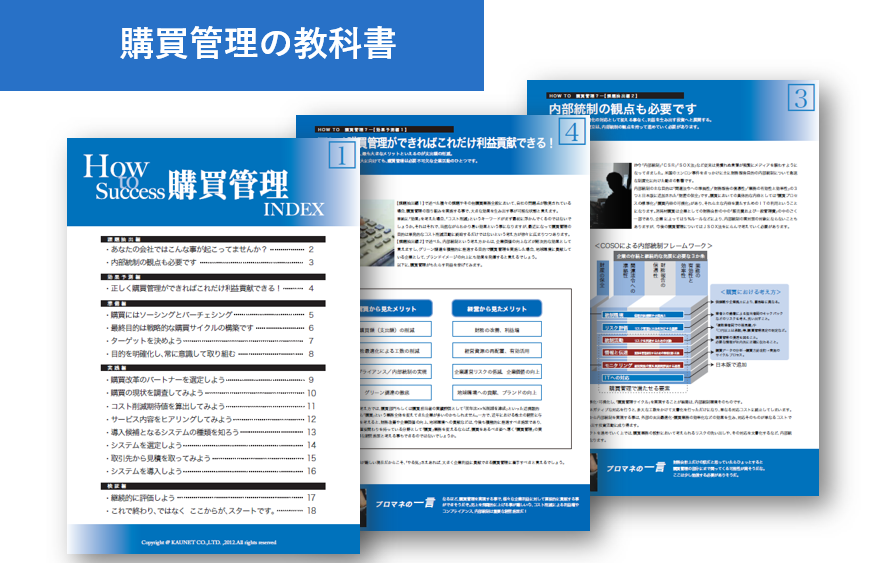
✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
購買管理の教科書「How to Success 購買管理」 >>
購買管理の基礎知識から実践までを詳しく解説。
品目の多様性により管理が煩雑になりやすい
副資材は、工具・消耗品・事務用品など多岐にわたる品目を含むため、管理が非常に複雑です。製造業では数万点に及ぶ品目を扱うこともあり、全体像の把握は難しいでしょう。購買状況を正確に把握できず、コスト管理や内部統制が不十分になるおそれもあります。
また、副資材は品目ごとに使用頻度や消費速度が異なるため、発注回数が増える傾向にあります。品目の多さから購入先も増えやすく、取引先ごとに異なる発注・支払フローに対応しなければなりません。
発注する部署・人が分散している
副資材の発注は各部門が独自に行うことが多く、管理が分散しやすい傾向です。発注プロセスがバラバラになり、全社的な購買状況の把握が難しくなります。
部門ごとに異なるサプライヤと取引することで、同じ品目で価格差が生じることもあるでしょう。
発注担当者の経験や知識によって調達効率に差が出やすく、属人化のリスクも高まります。
さらに、発注の分散化により、支払いプロセスも複雑化しやすくなります。
各部門が独自に発注を行うことで、請求書の管理や支払いのタイミングにばらつきが生じ、財務部門の業務効率低下につながるおそれもあるでしょう。
コスト管理が難しい
副資材は単価が低く発注頻度が高いという特徴から、コスト管理が難しくなります。
少数かつ購入頻度の低いロングテール品であることも多く、個別で価格交渉しにくい点が課題です。
都度の相見積は非合理的であり実施されないことが多いため、適切な購入先の選定や見直しがおろそかになりやすいでしょう。
その他にも、過剰在庫による保管・廃棄コストなど、隠れたコストが発生しやすい傾向にあります。
部門ごとの分散発注により、同一品目でも購入先や価格のばらつきが生じやすく、ボリュームメリットを活かしきれない企業も多いのが現状です。
主資材に比べて優先度が低い
製品の構成要素である主資材の管理に注力するあまり、副資材の管理がおろそかになっている企業は多いでしょう。
主資材は製品の品質や原価に直結するため、多くの企業で厳格な管理体制が整備されています。
一方、副資材は間接的な影響しか与えないと認識され、管理に十分なリソースが割り当てられません。専門の管理部署が設置されていない企業もあるでしょう。
その結果、副資材の購買管理がおろそかになり、無駄な工数・コストが発生したり、不正の温床になったりするおそれがあります。
副資材の管理不足により起こり得る4つのリスク

副資材の管理不足で起こり得るリスクは、以下の4つです。
- 生産ラインの停止リスク
- コスト増加リスク
- 作業効率の低下リスク
- 不正のリスク
企業の生産性に関わる大きなリスクにつながるため、この機会に副資材の購買管理を見直しましょう。
副資材の購買管理にお悩みの方は、以下の資料を参考にしてみてください。購買管理に関するよくあるお悩みや、その解決策についてわかりやすく解説しています。
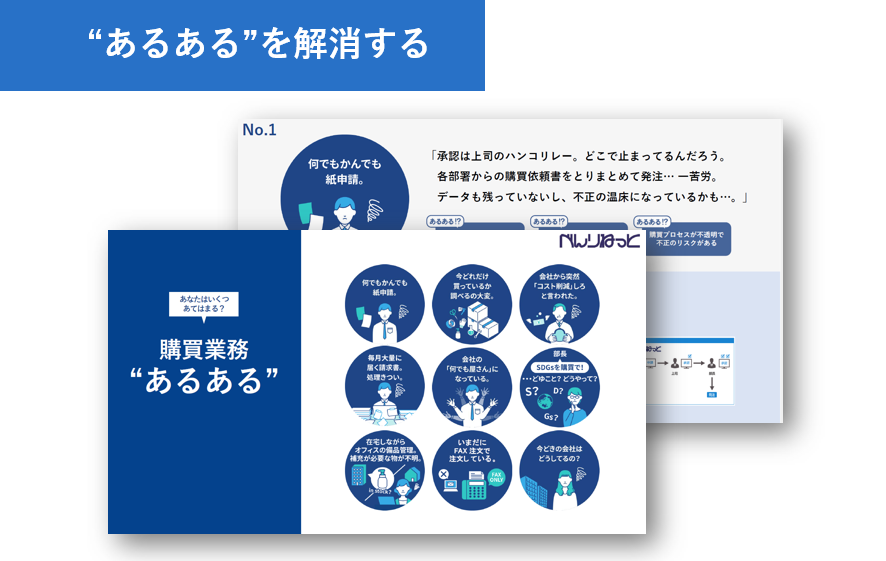
✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
購買業務 の""あるある""解決策集 >>
お客様と接する中でたどり着いた9つの"あるある"とその解決策を解説。
生産ラインの停止リスク
副資材の管理不足は、生産ラインの突然の停止を引き起こすリスクがあります。
たとえば、必要な工具や消耗品が適時に供給されないと、製造プロセスを中断するおそれがあるでしょう。とくに、特殊な溶接ガスや精密測定器具などの重要な副資材が欠品すると、生産活動は即座に停滞します。
生産ラインの再開には時間やコストが必要となり、全体的な生産効率の低下につながります。生産ラインの停止は納期遅延や顧客との信頼関係の損失につながり、長期的には企業の評判や市場シェアに悪影響を及ぼしかねません。
コスト増加リスク
副資材の管理不足は、予期せぬコスト増加を招くリスクがあります。計画的な調達ができず、ボリュームディスカウントの機会を逃し、小口発注が増えてコストが膨らむためです。各拠点・部署ごとに発注を行っている場合、全社の購買状況を正確に把握できず、無意識のうちに無駄な支出が発生しているケースが多いです。商品や購入先が分散したり、まとまった購買データが入手しづらかったりする可能性も高く、ボリュームを生かした価格交渉が難しくなります。
また、管理不足により適切な購入先の選定もおろそかになり、妥当な価格で調達できないおそれもあります。
副資材のコストに課題を感じている方は、以下の資料をご活用ください。コスト削減に向けた取り組みを、4ステップで実践的に解説しています。
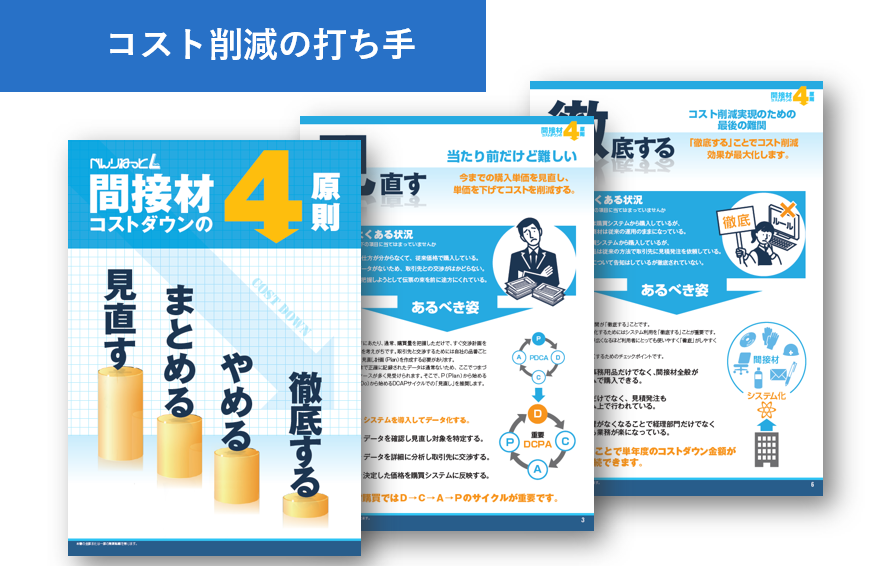
✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
間接材コストダウンの4原則 >>
コストダウンの4原則とその取り組み方を解説。
作業効率の低下リスク
アナログな管理により、購買業務の効率が低下するおそれがあります。
発注依頼や承認作業を紙で行ったり、発注先ごとにオンライン・FAX・電話などの発注方法を使い分けたりしている場合、購入にかかる工数が増大するだけでなく、ミスも起こりやすくなります。
また、発注拠点や購入先ごとに支払いプロセスが分散することで、経理部門の業務負荷も増大するでしょう。
非効率な業務環境によって、本来注力すべきコア業務に時間が割けなくなるリスクがあります。
不正のリスク
副資材の管理不足により、サプライヤとの利益相反取引や、社内での不正行為が起こるおそれがあります。特定のサプライヤを優先する代わりに私的利益を得るケースや、過剰調達や高額発注を通じた横領が典型的です。
なかでも、購買担当者とサプライヤが私的利益を共有する関係を築く「キックバック」は、発覚しない限り長期間継続する特性があります。
購買業務が属人化している場合、権限の集中によって他者によるチェックが行き届かず不正が発見されにくくなるでしょう。
問題が起こった際も、購買取引の履歴が残っていない場合は原因の特定が困難です。
不正防止には、組織全体の意識改革と透明性の確保が欠かせません。具体的には、購買管理規定の作成や職務分掌の徹底、購買プロセスの見える化が有効です。
自社の購買管理における内部統制に課題を感じている方は、以下の記事を参考にして購買プロセスを見直してみましょう。

✓ 関連記事もチェック
購買プロセスにおける内部統制とは?強化への4ステップを解説 >>
内部統制の重要性やリスク、内部統制を強化するための4ステップを解説。
副資材を効率よく管理するなら「購買管理システム」

副資材の購買管理は、主資材と比較して優先度が低くなりやすい傾向です。しかし、不適切な管理によって、現場の負担が増して企業全体の生産効率が低下するおそれがあります。
副資材を効率的に管理するためには、購買管理システムの導入がおすすめです。購買管理システムは、見積依頼から検収・支払までの一連の購買プロセスを電子化します。
副資材の管理にシステムを導入するメリットは、以下の3つです。
- 購買コストを削減できる
- 購買業務の効率が向上する
- ヒューマンエラーや不正の防止につながる
購買管理システムで実現できることを明確にし、導入を検討してみてください。
システムの導入をすでに検討している方は、以下の記事もご参考ください。

✓ 関連記事もチェック
購買管理システムとは?便利な機能や導入メリットを解説 >>
購買管理システムの機能やメリット、システムの選び方を解説。
以下の資料では、購買管理システムの導入で起きた失敗事例と原因について解説しています。自社でのシステム導入を成功させるために、ぜひお役立てください。
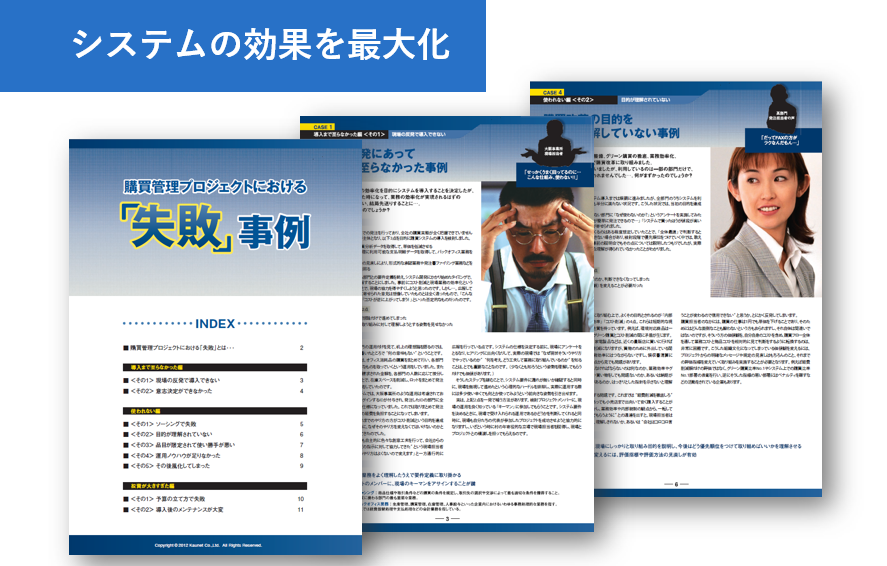
✓ お役立ち資料を無料ダウンロード
購買システム導入の失敗事例 >>
購買管理でよくある失敗と成果に繋げるためのポイントを解説。
購買コストを削減できる
購買管理システムで全社の購買を可視化することで、適切なコスト改善策を講じられます。たとえば、部署ごとにばらついていた購入先や商品を統一することで、ボリュームメリットを活かしたコスト削減を図れます。
システムでの購買に統一することで、全社を通して値引き価格での購入を徹底することも可能です。
また、外部サイトのカタログを一括で比較できる「サイト間一括検索機能」を活用すれば、いつでも最適な価格で副資材を購入可能です。
以下の記事では、コスト削減に向けて、ひとつのプラットフォームで集中購買できる点に魅力を感じて導入した事例を紹介しています。

✓ 導入事例をチェック
「ヤンマーホールディングス株式会社」様 >>
コスト削減を具体的にイメージできたことが導入の決め手に。
購買業務の効率が向上する
購買ワークフローに購買管理システムを導入することで、発注書作成から検収までをデジタル化し、手作業を大幅に削減できます。
たとえば、以下の機能によって業務改善とコスト削減を両立できます。
| 機能 | 概要 |
| 一括見積機能 | 複数取引先へ見積もり依頼から採用・不採用通知まで自動で送付 |
| 承認ワークフロー | 発注・承認を完全に電子化 |
ERPシステムや自社の基幹システムと連携すれば、支払・会計処理などのさらなる業務効率の向上が期待できるでしょう。
以下の記事では、システムの導入によって、発注工数とコスト削減が実感できた事例を紹介しています。購買管理の業務効率化に力を入れたいと考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「カルビー株式会社」様 >>
グループ全体で発注工数を50%削減。
ヒューマンエラーや不正の防止につながる
購買管理システムは、ヒューマンエラーを防ぎアクセス制御や承認プロセスで不正を防止します。具体的には、システムの活用によりこれまで手作業で行っていた入力や計算を自動化することで、データの正確性が向上します。
また、アクセス権限をユーザーの役割に応じて細かく設定することで、不正アクセスや情報漏えいの防止に役立つでしょう。
購買履歴はすべて記録され、いつでも閲覧できるため、不正が発覚した際も迅速に対応できます。
以下の記事では、購買データがWeb上に記録されることで不正の防止につながった事例を紹介しています。自社の購買管理における内部統制に課題を感じている方は、一度チェックしてみてください。

✓ 導入事例をチェック
「日本貨物鉄道株式会社」様 >>
承認過程や購買実績を見える化してコンプライアンスを強化。
副資材の購買管理を見直して企業の生産性を上げよう

副資材の管理は軽視されがちですが、管理が不足することでさまざまなリスクを引き起こします。
副資材の管理が難しい理由として、品目の多様性による管理の煩雑さや、発注部署の分散などがあげられます。
しかし、適切な管理体制を構築することで、企業の生産性や収益性を大きく向上できるでしょう。
副資材の購買管理における課題を解決するためには、購買管理システムの導入が効果的です。システムを活用することで、購買コストの削減や業務効率の向上、不正の防止など、多くのメリットが得られます。
副資材の重要性を認識し、戦略的な管理体制を構築して企業全体の生産性と競争力を高めましょう。